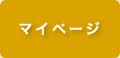こんにちは!ここりん・・・じゃなく、今日も社員です。
桜の季節もあっという間に過ぎ・・・
ゴールデンウィークが待ち遠しい今日このごろ
名古屋支店から碧南本社へ車で向かう途中の田んぼで、
田植え前の準備をしている農家さんの姿を見かけました。
そういえば、そろそろ九重みりんで使用しているモチ米も
田植えシーズンを迎える時期だぁ・・・
九重みりんでは、九州から北海道までヒヨクモチ、キタユキモチ、
ジュウゴヤモチ、ココノエモチなど製品に合わせて
いろいろなモチ米を使っているのですが、
社内で聞いたところ早稲と呼ばれる田植えの早いココノエモチ
という品種の田植えが愛知県内で来週はじまるようです。
九重みりん田植えといえば、6月中旬とだいぶ先になりますが、
毎年恒例の社員による田植えが行われます。
みりんの原料であるもち米が、苗からどのようにして育ち収穫され、
みりんの原料となるのかを社員全員で体験しようと
2009年から始まったこの試みも今年でもう7年目。
初年度は田んぼに入ったこともない社員が大半で
農家さんに苗の持ち方から教えて貰っていたのに、
今では社員の手植えも慣れたものです。
まだ、田植え前の田んぼを眺めながら、
今年もたくさん採れるかな~と思ってしまう自分・・・、
なんて気が早い・・・
とりあえず、今年も田植えをがんばるぞー!(まだ再来月だけど・・・)

みりん 味醂 三河みりん
本みりんの通販
日本最古の味醂醸造 九重味淋【公式ブログ】