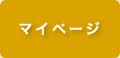こんにちは!ここりん・・・じゃなく、社員です。
なぜか今、無性にたけのこが食べたい気分です。
みなさん食べてますか???
ちょっと前にたけのこの話が出まして、
それを思い出したら食べたくなってきました。
その前に少したけのこのことを調べてみました
タケノコとはご存知のとおり竹の芽の部分です。
竹にはいくつかの種類がありますが、
たけのことはすべての竹の芽の総称として使われています。
竹は意外にもイネ科にあたり、温暖な地域に多く生えています。
イネ科とはびっくりですね~。
イメージわかないです(>_<)
たけのこは種類も多く、70種類ほどあるそうで、
食用にされているものは孟宗竹をはじめ、ほんの数種類なんだそうです。
春の味覚を代表する食材です。
たけのこの名前の由来なんですが、
その名前「筍(たけのこ)」は一旬(10日間ほど)で
あの「竹」までに生長してしまうからだそうです。
だから、食べられる期間もほんの一瞬、
土から出るかで無いかとい うときだけなので、目が離せません。
そんなに成長が早いにもかかわらず、
竹の寿命は百年以上とも言われています。
んー、不思議です。
食べれる期間が10日間ほどって、すごく驚きました。
そんなに早く成長してしまうんですね。
しかも、土から出るか出無いかくらいなら
見落としてしまいそうですよね(>_<)
いかん、ますます食べたくなってきました・・・・
たけのこの入った炊き込みご飯!!!!
焼いてしょうゆをたらして食べる・・・・
今晩はムリでも週末には出してもらおーっと
みりん 味醂 三河みりん
本みりんの通販
日本最古の味醂醸造 九重味淋【公式ブログ】